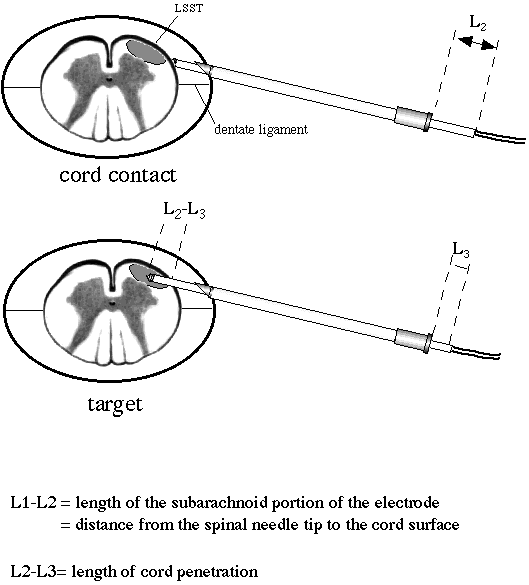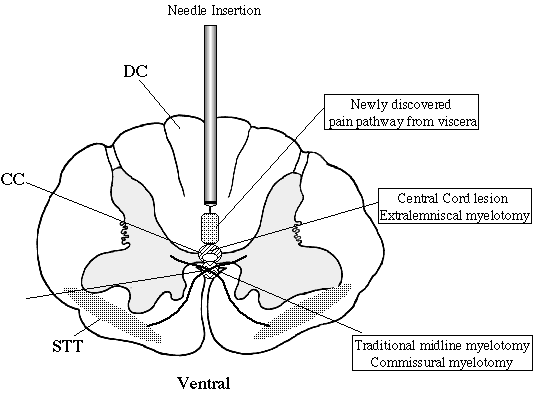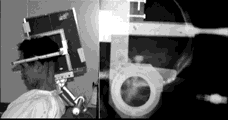経皮的コルドトミーとCentral Cord Lesioning
要旨
癌性疼痛に対する経皮的コルドトミーとCentral Cord
Lesioningについて、著者らの経験に基づいてその背景と現状を中心に説明する。高位脊髄レベルで外側脊髄視床路を選択的に凝固破壊する経皮的コルドトミーは悪性腫瘍による一側性の壁側痛に対しては良好な除痛効果が得られる優れた除痛法である。しかし癌性疼痛のうち骨盤内臓器の悪性腫瘍によるものでは内蔵痛と壁側痛が混在していることが多く、経皮的コルドトミーによる外側脊髄視床路切截術をたとえ両側性に行っても除痛が困難なことがある。このような疼痛に対してはむしろ脊髄中心管近傍を経皮的に凝固するCentral
Cord Lesioningのほうが適応になることが多い。Central Cord
Lesioningによる除痛の理論的背景は長年に渡り明確にされていなかったが、近年内蔵痛を伝導する上行路が脊髄後索の正中深部に同定され、臨床的にも確認されるようになった。内蔵痛の機序の基礎的研究とともに臨床的にも今後の発展が期待される領域である。
キーワード: 経皮的コルドトミー、脊髄中心部切截術、内蔵痛
上位頚髄レベルで脊髄における温痛覚の伝導路の中心をなす外側脊髄視床路を選択的に凝固破壊する経皮的コルドトミーは古くから行われている癌性疼痛の緩和法として80%以上の症例で十分な除痛の得られる優れた方法である1,2,3)。すなわち全身状態の悪い症例でも局所麻酔下に施行でき、対象を的確に選択しに行った場合、その効果は確実で、副作用も少ない。しかし骨盤腔内臓器の悪性腫瘍による疼痛のようにしばしば痛みが両側性で、しかも内蔵痛と壁側痛が混在するような場合には、少なくとも両側手術が必要であり、合併症の頻度も増加する4)。
これに対し、上位頚髄の中心管近傍を凝固破壊するCentral Cord
Lesioning5,6)は、一回の経皮的手術で両側性の広範な除痛を得ることが可能で骨盤腔内臓器の悪性腫瘍による疼痛にはむしろこの方が適応になることが多いと考えられる。従来この手術の除痛機序としては、脊髄中心管周囲の灰白質に多シナプス性の疼痛の上行路が存在すると考えられてきた。しかし最近、内蔵痛を伝導する経路が脊髄後索の深部に同定され7,8)、中心管近傍の灰白質よりもむしろ正中深部の後索線維の破壊による除痛機序が有力視されている。
経皮的コルドトミー
【背景】脊髄の前側索の障害により対側の温痛覚が消失するという臨床所見に基づいて、1912年にSpiller
&
Martin9)が直視化に脊髄の前側索を切截術を行ったのがコルドトミーの始まりである。この方法はその後Mullanら10)、Rosomoffら11)によって局所麻酔下に経皮的に行われるようになり、現在の方法の基礎となった。最も良い適応としては、C5以下のレベルにある一側性の癌性疼痛であるが、両側性の場合には1-2週間間隔をあけて両側のコルドトミーを行うことも可能である。この場合、夜間呼吸抑制や尿閉などの合併症が問題となることがあるが、比較的細い
(直径0.4mm
程度)双極電極針を用いることである程度これらは回避可能である1,12)。go
top
【手術方法】患者を仰臥位にし、まず側面レントゲン透視で見ながら上位頸椎脊椎管が水平になるように頭部を固定する。 特別な固定具もあるが13)、通常の手術台と円座およびテーによる固定でも十分可能である。水平にするのは頭蓋内に造影剤や空気ができるだけ入らないようにし、脊髄造影を効果的に行うためである。必要に応じpentazocine
15mg、diazepam
5mg程度を静脈内投与するが、患者と十分会話できる状態でなければならない。疼痛と対側の乳様突起先端から1cm尾側で1cm背側を皮膚の刺入点の目安として、23Gのカテラン針を用いてC1-C2
spaceへ至る経路を1%キシロカイン10ml程度で局所麻酔を行う。このとき硬膜外腔に達した場合0.5ml程度のキシロカインを注入し局部の硬膜外麻酔を行うと硬膜穿刺時の痛みが軽減できる。側面レントゲン透視を見ながら19Gの穿刺針で脊椎管の前後径の中央より1-2mm程度腹側を目標として髄液腔を穿刺する。穿刺の方向は完全に水平ではなく、穿刺方向が脊髄断面上での外側脊髄視床路の長軸と合うように角度をつける必要がある。この角度は髄液腔を穿刺した時点で80mmの穿刺針の半分から近位3分の1程度の部分が側面レントゲン上で脊椎管後面に一致する程度である(Fig.1)。硬膜の抵抗を感じたら勢いよく硬膜を貫通させるが、脊髄自体を穿刺しないように注意する。またこの穿刺針の全長、コルドトミー針が先端まで達した場合の残りの長さをあらかじめ計測しておく(Fig.2)。
特別な固定具もあるが13)、通常の手術台と円座およびテーによる固定でも十分可能である。水平にするのは頭蓋内に造影剤や空気ができるだけ入らないようにし、脊髄造影を効果的に行うためである。必要に応じpentazocine
15mg、diazepam
5mg程度を静脈内投与するが、患者と十分会話できる状態でなければならない。疼痛と対側の乳様突起先端から1cm尾側で1cm背側を皮膚の刺入点の目安として、23Gのカテラン針を用いてC1-C2
spaceへ至る経路を1%キシロカイン10ml程度で局所麻酔を行う。このとき硬膜外腔に達した場合0.5ml程度のキシロカインを注入し局部の硬膜外麻酔を行うと硬膜穿刺時の痛みが軽減できる。側面レントゲン透視を見ながら19Gの穿刺針で脊椎管の前後径の中央より1-2mm程度腹側を目標として髄液腔を穿刺する。穿刺の方向は完全に水平ではなく、穿刺方向が脊髄断面上での外側脊髄視床路の長軸と合うように角度をつける必要がある。この角度は髄液腔を穿刺した時点で80mmの穿刺針の半分から近位3分の1程度の部分が側面レントゲン上で脊椎管後面に一致する程度である(Fig.1)。硬膜の抵抗を感じたら勢いよく硬膜を貫通させるが、脊髄自体を穿刺しないように注意する。またこの穿刺針の全長、コルドトミー針が先端まで達した場合の残りの長さをあらかじめ計測しておく(Fig.2)。
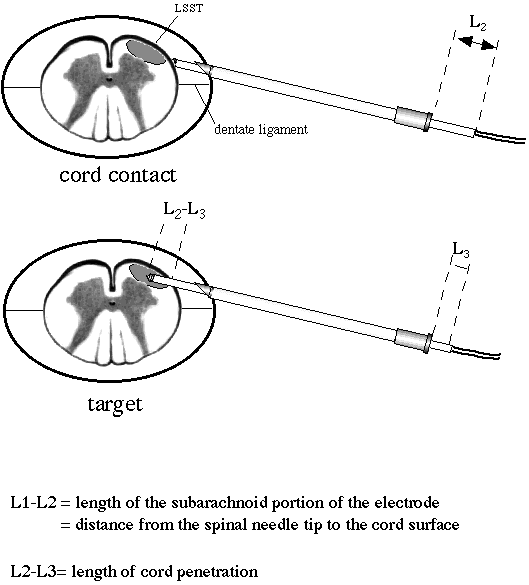
|
Fig.2: 穿刺針と電極針の長さの計測
L1: 穿刺針と電極針の長さの差、L2: Cord
contact時の電極針の残りの長さ、L1
L2が穿刺針先端から脊髄表面への距離となる。L3:
外側脊髄視床路を穿刺したときの電極針の残りの長さ、L2-L3が脊髄内に入っている電極針の長さで通常3
4mmとなる、LSTT: 外側脊髄視床路
|
髄液の流出を確認したら、卵管造影用の油性造影剤lipiodol
1mlと髄液1ml、空気5mlを入れた注射器をよく撹拌して造影剤がemulsionとなるようにしたものをゆっくりと注入する。注入の状況を側面レントゲン透視で観察すると脊髄腔後縁と歯状靱帯に油性造影剤の細かい粒が乗り、これらが確認される(Fig.3)。また空気による陰性造影効果で脊髄前縁が描出される。これらの像は最近の性能の良い透視装置と画像停止機能を用いて十分観察できるが、フィルムによる撮影を行ったほうが詳細な情報が得られる。外側脊髄視床路は歯状靱帯よりもやや腹側に位置するので、たとえ髄液の流出を認めても、脊髄腔穿刺針がこの部位から大きくずれている場合には再度穿刺をやりなおす必要がある。また、穿刺針が歯状靱帯を貫通している場合には穿刺針先端を動かすと同時に脊髄も動いてしまい先端部位の調節が困難となることがある。コルドトミー用電極針を穿刺針に挿入すると、電極針の残りの長さがFig.2に示したL1よりも数ミリ短くなったところで、電極針先端が脊髄の表面にあたり弾力性の抵抗を感じることができる(cord
contact)。透視でこの時に電極針先端が歯状靱帯よりも1-2mm腹側にあることを確認する。電極針が脊髄の軟膜を貫くときには痛みが生じるので患者にその旨を伝えたうえで、電極針を勢いよく3-4mm脊髄内に挿入する。ある程度勢いよくしなければ脊髄が押されて偏位してしまう。ここで5Hz,
1-2Vの電気刺激を行い手足に筋収縮が見られないことを確認する。電極針先端が背側に偏位し錐体路に入っている時には手足のtwitchが見られる。また、電極針先端が外側脊髄視床路に入っていても、この刺激条件では疼痛は誘発されずC1-2の脊髄神経によって支配される項部筋の収縮が見られる。次に刺激を50Hzとし徐々に強度を上げていくと0.5-1V程度で対側に熱感や疼痛が惹起される。外側脊髄視床路の線維はsomatotopicな配列を示し、深部内側が頸部、浅層部外側が腰仙部からの線維が走っているので疼痛が惹起される部位を参考にしながら電極針を1mmずつ深くしたり浅くしたりしながら電気刺激によって誘発される反応の部位が自発痛の部位に一致するように調節する。この時点で開口位の前後像のレントゲンで電極針先端の位置を最終的に確認する(Fig.4)。このときには第2頸椎の歯状突起の正中を脊髄の正中とみなすとよい。電気刺激によって定型的な反応が得られない場合には決して凝固巣を作製してはならない。高周波凝固は電極先端に温度センサーがついている場合にはまず45℃、30秒で試験的な凝固巣を作成し、除痛効果と麻痺のないことを確認したうえで、70℃、30秒で永久的な凝固巣を作成する。温度センサーのない場合には高周波電流をモニターしながら徐々に30-50mA程度まで上げていく。これは患者に凝固と同側の手を挙上させ指折りを繰り返させながら麻痺が出現しないかを注意深く観察しながら行う。30秒の通電で除痛効果をpinprick
testで確認し、最終的にはインピーダンスが急に上昇することで永久凝固巣ができたことを確認する。術後は髄液の流出による頭痛が問題になることがあり、必要に応じて多めの輸液と鎮痛剤を用いる。

|

|

|
|
Fig.1: C1-C2スペースよりの穿刺方向
頚部脊椎管はは水平にし穿刺針はやや腹側を向くようにする。
|
Fig.3: 油性造影剤による歯状靱帯の同定
歯状靱帯と脊椎管後縁が明瞭に描出されている
|
Fig.4: 前後像での電極針先端の確認
第二頸椎歯状突起の幅が脊髄の幅にほぼ一致する
|
go top

【合併症】一側性に行い電気刺激で疼痛反応が誘発される部位だけを注意深く凝固した場合には重大な副作用はみられない。術中の髄液流出による頭痛、嘔吐には多めの補液と制吐剤などの対症療法で対応可能である。両側の痛みの場合には、両側のコルドトミーが可能であるが、少なくとも1-2週間の間隔を開けて行わなければならない。術後の留意点としては呼吸抑制、とくに夜間睡眠時の無呼吸が生じる可能性がある。これは自発呼吸機能の下行路である延髄網様体脊髄路と外側脊髄視床路が近接している(Fig.5)ため14)で、両側性でなくとも肥満患者や肺癌などにより呼吸機能が低下している例、脊髄、脊椎転移で肋間筋麻痺がある例などではとくに注意する必要がある。また、換気障害でCO2が蓄積しがちであるのでむやみな酸素投与も危険である。また、自律神経路も外側脊髄視床路に近接しているため(Fig.5)、排尿障害も生じることがある。これは通常は1-2週間で改善するが、骨盤内臓器癌では改善困難なことも多い。
コルドトミー後数カ月から半年程度経過してから神経因性疼痛のひとつであるコルドトミー後の求心路遮断性疼痛(deafferentation
pain)が発生することがあり15)、これがコルドトミーが良性疾患による疼痛への適応にならない理由である。逆に悪性腫瘍に合併した帯状疱疹後神経痛は、当然癌性疼痛ではないが、コルドトミーを行い良好な結果が得られた経験もある。いずれにせよ神経因性疼痛は通常の鎮痛剤には反応せず、抗けいれん剤や抗うつ剤の投与が有効な場合もある。
【今後の展望】経皮的コルドトミーは経口モルヒネ製剤の投与法が普及した現在、その必要性は低下しつつある。しかし、経口モルヒネ製剤や持続硬膜外ブロックなどと比較した場合の経済性や患者のADLの面から、癌性疼痛の管理に携わるものは常に念頭においておく必要があると考えられる。技術的には確立された方法であるが、レントゲン透視ではなくCTを用いる方法16,17),
水溶性造影剤を用いる方法18)など新しい進歩もみられる。さらに、詳細な臨床的観察から、脊髄視床路の大脳への投射様式19)や痛覚と温度覚の経路の違い20)などの新らたな知見もみいだされており、このような神経生理学的側面からの観察も重要であろう。go
top
Central Cord Lesioning
脊髄視床路は脊髄後角に起始し中心管前方で対側へ交差して前側索を上行する。したがってこの交差部を遮断することでその脊髄レベルに一致した皮膚節の両側性の除痛が可能である。これが高橋が別項に述べている
Midline MyelotomyあるいはCommissural
Myelotomyの理論である。この理論に基づいてHitchcockはC1-occipitalあるいはC1-C2スペースで後方から経皮的に電極針を挿入し頚部の両側性分節性の除痛を試みた。ところが驚いたことにこの術後に両側性のほぼ全身にわたる広範な除痛が得られたのである21)。詳細は文献を参照されたいが、この奇妙な現象はその後Schvarcz22,23)を含め多くの報告で確認されている5)。
この除痛の特徴はpinprick
testで針先が鋭か鈍かはわかるものの、鋭の場合でも患者は痛くないと報告することである。多数の臨床例からこの方法はびまん性の内蔵痛にも有効であることが示され、痛みの伝導は外側脊髄視床路だけでなく、脊髄中心管周囲の灰白質にも多シナプス性の痛みの上行路があることが示唆されるようになった5,22,23)。
実際にはFig.6に示すようにC1-occipital
spaceから穿刺し脊髄背側の正中で局所麻酔下に電極針を進めながら電気刺激を行うと、まず後索内側の線維が刺激され両側の下肢にびりびりとした感覚が誘発される。さらに進めるとこの下肢の感覚が消失する部位で胸腹部の深部にいやな焼けるような感覚が誘発されるようになる。脊髄背側からおよそ5mmのこの部位がCentral
Cord
Lesioningの凝固巣作成部位であるが、これが従来は脊髄中心管周囲の灰白質と考えられていたわけである。しかし最近内蔵からの痛みを伝える経路が後索深部の正中部に存在し頚髄核(主としてNucleus
gracilis)へ上行するという知見が動物実験で見いだされ7,24)、これに基づいて後索内の一部を破壊することにより内蔵痛が両側性に除痛されるという臨床例での報告もなされるようになった8)。すなわち脊髄の正中上には前方から脊髄視床路の前交連、中心管周囲灰白質、後索内の内蔵痛伝導路が配列していることになる(Fig.7)。これらの領域は狭いためにCentral
Cord
Lesioningの凝固巣作成部は中心管周囲灰白質だけでなく後索内の内蔵痛伝導路をも含んでいると考えられ、これが両側性内蔵痛に効果的である理由と推測される。
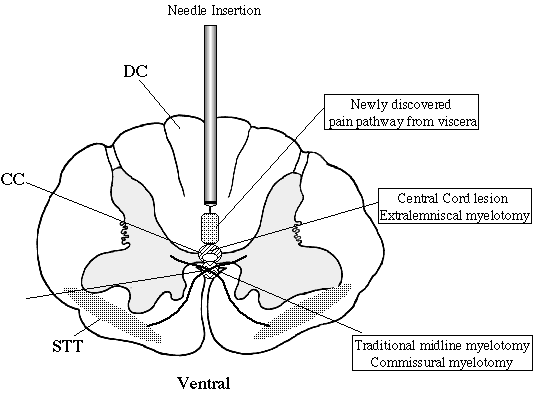
|
|
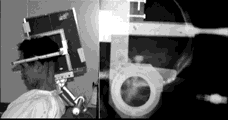
|
|
Fig.6: Central Cord
Lesioningにおける後頭骨・第一頸椎間後方よりの穿刺針の刺入
|

|
|
Fig.7: 脊髄視床路の前交連、中心管周囲の灰白質、および後索深部の内蔵痛の経路の位置関係、DC:
後索、CC: 脊髄中心管、AC: 前交連、STT: 外側脊髄視床路
|
Fig.8: 定位脳手術装置を用いたCentral
Cord
Lesioning、患者は坐位で局所麻酔下に後方より穿刺している
|
Central Cord
Lesioningは基本的には上位頚髄を目標部位にできる特別の定位脳手術装置を用いて坐位で行う6)が(Fig.8)、KanpolatらはCT室内でfree
handによる方法を報告しており16)、今後このような方法がより実用的であると考えられる。また、Nautaの報告8)のように全身状態の許す症例では全身麻酔下に限局的椎弓切除により特別の装置を用いずとも行うことができる。いずれにせよ経口モルヒネなど他の治療法によっても十分な除痛が得られないような骨盤内臓器癌による癌性疼痛にはこのような外科的治療も積極的に考慮する価値がある25)と考えられる。go
top
参考文献
go top
 特別な固定具もあるが13)、通常の手術台と円座およびテーによる固定でも十分可能である。水平にするのは頭蓋内に造影剤や空気ができるだけ入らないようにし、脊髄造影を効果的に行うためである。必要に応じpentazocine
15mg、diazepam
5mg程度を静脈内投与するが、患者と十分会話できる状態でなければならない。疼痛と対側の乳様突起先端から1cm尾側で1cm背側を皮膚の刺入点の目安として、23Gのカテラン針を用いてC1-C2
spaceへ至る経路を1%キシロカイン10ml程度で局所麻酔を行う。このとき硬膜外腔に達した場合0.5ml程度のキシロカインを注入し局部の硬膜外麻酔を行うと硬膜穿刺時の痛みが軽減できる。側面レントゲン透視を見ながら19Gの穿刺針で脊椎管の前後径の中央より1-2mm程度腹側を目標として髄液腔を穿刺する。穿刺の方向は完全に水平ではなく、穿刺方向が脊髄断面上での外側脊髄視床路の長軸と合うように角度をつける必要がある。この角度は髄液腔を穿刺した時点で80mmの穿刺針の半分から近位3分の1程度の部分が側面レントゲン上で脊椎管後面に一致する程度である(Fig.1)。硬膜の抵抗を感じたら勢いよく硬膜を貫通させるが、脊髄自体を穿刺しないように注意する。またこの穿刺針の全長、コルドトミー針が先端まで達した場合の残りの長さをあらかじめ計測しておく(Fig.2)。
特別な固定具もあるが13)、通常の手術台と円座およびテーによる固定でも十分可能である。水平にするのは頭蓋内に造影剤や空気ができるだけ入らないようにし、脊髄造影を効果的に行うためである。必要に応じpentazocine
15mg、diazepam
5mg程度を静脈内投与するが、患者と十分会話できる状態でなければならない。疼痛と対側の乳様突起先端から1cm尾側で1cm背側を皮膚の刺入点の目安として、23Gのカテラン針を用いてC1-C2
spaceへ至る経路を1%キシロカイン10ml程度で局所麻酔を行う。このとき硬膜外腔に達した場合0.5ml程度のキシロカインを注入し局部の硬膜外麻酔を行うと硬膜穿刺時の痛みが軽減できる。側面レントゲン透視を見ながら19Gの穿刺針で脊椎管の前後径の中央より1-2mm程度腹側を目標として髄液腔を穿刺する。穿刺の方向は完全に水平ではなく、穿刺方向が脊髄断面上での外側脊髄視床路の長軸と合うように角度をつける必要がある。この角度は髄液腔を穿刺した時点で80mmの穿刺針の半分から近位3分の1程度の部分が側面レントゲン上で脊椎管後面に一致する程度である(Fig.1)。硬膜の抵抗を感じたら勢いよく硬膜を貫通させるが、脊髄自体を穿刺しないように注意する。またこの穿刺針の全長、コルドトミー針が先端まで達した場合の残りの長さをあらかじめ計測しておく(Fig.2)。